私たちは知っているものしか見ることができない

17世紀のオランダの画家フェルメールの「稽古の中断」という絵に描かれた楽譜が本物の楽譜ではないか。だとすれば、この絵から、音楽が聞こえてくるのではないか。そう思った生物学者の著者が探求を始める。17世紀は著者によれば、科学と芸術が「極めて親しい場所にあった」という。
探求の結果、フェルメール絵画の細部に著者は「隠された次元」を発見したというのだ。まことにスリリングな企てだ。
巻頭にフェルメールの絵画が贅沢に並べられている。
そのあと、すぐにフェルメールの話に突入するのかと思いきや、地図とDNAの話になる。読んでいるうちに、世界観を語ることがフェルメールを語ることに後でつながるのだなと思い至る。地図が不要のひとの世界の捉え方は言語でいうメトニミカルな把握とそっくりだ。地図が必須のひとのそれはメタフォリカル。ローマン・ヤーコブソンの言葉でも語れそうなのがおもしろい。
著者によればDNAは全体像を示す地図ではない、さらに実行命令が書かれたプログラムでもないという。これは驚きだ。一般の常識に反する。DNAはせいぜい材料表またはカタログだという。細胞の内部で使う部品のリストに過ぎないと。言語でいえば作家や詩人ごとの語彙リスト、いわば「辞書」みたいなものか。
そのあとは、昆虫少年だった著者が、新種を発見したと興奮して国立科学博物館に行く話になる。そこで少年は日本を代表する昆虫学者、黒澤良彦に出会い、黒澤のような昆虫学者になりたいと思う。ところが、著者が本格的に勉強を始めた頃、黒澤のような純粋な昆虫学者こそが絶滅危惧種になりかけていた。
1980年代初頭に分子生物学の潮流がやってくる。著者は、昆虫採集の代わりに、細胞の森の中に分け入り、隠れている遺伝子を探し出し、その地図を作る研究をすることになる。遺伝子マッピングだ。
そのあと、17世紀オランダのデルフトに生まれたアントニー・ファン・レーウェンフックという名の微生物の狩人のことを著者は知る。岩波書店から出されていた大変な悪書『微生物の狩人』の中で。顕微鏡を使って組織学の創始者となった博物学者だ。
その後、大学で教えるようになった著者は、学生に顕微鏡を使って細胞の観察をさせる。見えるものをノートにスケッチさせてみると、学生が描くのはとりとめのない絵だった。そこで、著者は、〈私たちは知っているものしか見ることができない〉ことに気づく。
ここまできてようやく、フェルメールに話が接続する。長い遠回りのようにも見えるが、フェルメールの絵の本質を知るためには欠かせない道のりであったことが読者には実感できる。
知的スリルに満ちた書。
近未来なのに懐かしい

著者初の短篇集。どの短篇にも藤井太洋の世界観がしっかり刻まれ、物語の世界を読者も共有することができる。
収められた短篇は次の通り(括弧内は初出)。
1. コラボレーション(SFマガジン、2013)
2. 常夏の夜(『楽園追放 rewired』、2014)
3. 公正的戦闘規範(『伊藤計劃トリビュート』、2015)
4. 第二内戦(『AIと人類は共存できるか?』、2016)
5. 軌道の輪(書き下ろし)
初めに結論をいうと、傑作だ。科学技術が発展した近未来のその先を描きだすSFながら、どこか懐かしさをおぼえる。
技術的にバリバリの尖端的な内容でありながら、妙にヒューマンなタッチが失われることなく、登場人物たちと同じ世界を仮想体験する心地が味わえる。爽快な体験といっていい。
1はデビュー長篇『Gene Mapper』の前日譚的スピンオフ。〈インターネット後〉の世界をえがく。ふだん UNIX を使っているひとには居心地がよい作品。ネットワークと決済という今日的な話題の先がほの見える。
2は量子アルゴリズムが人類社会を革新する世界をセブ島を舞台にえがく。台風の被害にあえぐセブ島の混乱を収拾するため、現地へ向かう経路の最適化という問題が持ち上がるが、それを意外な人物が量子コンピューティングを応用して解決する痛快な物語。〈人類の知の先端(エッジ)は、在る未来への挑戦に変わった〉という名言が出るのはこの作品だ。量子ネイティブの世代の夜明け。
3は主人公「公正」が近未来中国の対テロ戦争に巻き込まれる物語。
4は保守と革新に分断されたアメリカを舞台に、保守の新独立国に潜入する物語。
5は木星と地球をめぐる、イスラーム的世界観の未来。
[Kindle 版]
コーモラン・ストライク・シリーズ第4作
Robert Galbraith, Lethal White (2018)
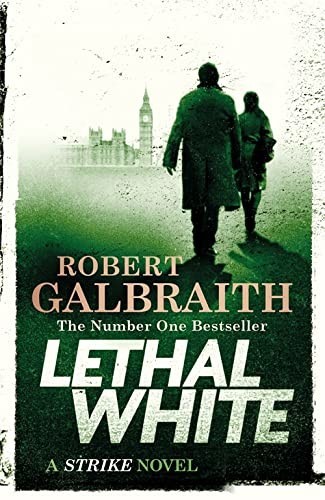
600ページを超える大作。プロットは複雑。英国の国務大臣の謎の死をめぐり、多数の人脈がからみ、ストライクとロビンによる捜査が進展する。通常、ミステリの最後の方では謎解きがあり、ペースが落ちるものだが、本作は最後の5%あたりからものすごいサスペンスが新たに展開し、息もつかせない。
作品を読んでの満足度ということになると、読者により変わるだろう。私の場合は、本シリーズの文体に魅せられており、英国の本格小説の濃厚な味わいをこれまでの3作で楽しんできた。が、本作に関しては、やや文体の密度が薄いように感じられる。
(作者は実は女性であるが)男くさい、英国英語らしいひねりの効いた文章に唸らされるという場面が、これまでの作品に比べてやや少ない。唸らされる箇所が決してない訳ではないのだが、600ページもあると、これまでと同じ数だけそういう箇所があったとしても、全体としては薄められた印象になる。
ラテン語の詩が重要な役割を果たす。これは、カトゥルスの詩に親しんでいるような読者なら自然に読めるだろうが、原語でカトゥルスを読んだことのない人にはやや敷居が高いかもしれない。本作では捜査の相棒のロビンがまったくラテン語を解しないために、事件の肝腎のヒントを見落としてしまうことになる。
副プロットであるロビンの夫婦関係の話は、夫のマシューに人間的魅力が乏しいため、やや辟易する。この部分にこれほど紙幅を割く必要があるのだろうか。これくらい書くのであれば、ロビンとストライクの関係も同じくらい書いてくれないと、バランスが悪い。逆に、ストライクとシャーロットのエピソードはおもしろい。ストライクの人間性を浮かび上がらせるからだ。ともかく、本シリーズにおいては主人公のストライクが何と言っても強烈な個性の持ち主であり、魅力が大きいので、人間関係についてはストライクをからめた形で描く部分がいちばんおもしろい。
タイトルは馬に関係する。馬の話題がかなり出てくるので、興味のある人にはおもしろいだろう。
[Kindle 版]
Ann Cleeves のシェトランド・シリーズ第7作
Ann Cleeves, Cold Earth (2016)

このシリーズを読み終えるといつも虚脱感に襲われる。
作品世界からお別れしなければならないからだ。
今回もたっぷりシェトランドのミステリに浸かった。風や雨や冷気が伝わってくるような筆致には、毎度のことながら、ぞくぞくさせられる。
姿の見えない犯人を捜査で絞って行く間は怖くはないのだが、殺人犯が現れた時には殺気が漂い、一気にサスペンスが盛上がる。
Shetland Island series の第7作。(その前にToo Good To Be True [novella, 2016]がある。) Tain と呼ばれる場所で地滑りが起きる。そこに女性の死体。誰なのか。捜査を進めるなか、別の殺人事件が起きる。両者は関係しているのか。謎は深まる。
シェトランド島の狭いコミュニティの中の人間関係の複雑さを捜査陣が解いてゆく。捜査チームは主人公 DI Jimmy Perez と上司 DCI Willow Reeves, および DC Sandy Wilson の3人だ。本作ではそれぞれが役割を十分に果たし、精密に捜査してゆく。特に Perez と Reeves のロマンティックな関係は前作あたりから気になっていたが、本作では読みごたえがある。
※DI=Detective Inspector「警部補」、DCI=Detective Chief Inspector「警部」、DC=Detective Constable「巡査」
スコットランド英語の雰囲気が随所で楽しめる。これほどローカル色豊かで味わいのあることばはめったにない。英国のミステリ小説が好きな人には文句なくお勧めできる。
[Kindle 版]
歯と髪はその人の源だ
キム・チュイ『小川』(彩流社、2012)

ベトナム系カナダ人の自伝的小説。
アジア系の北米の作家は多数存在する。その中に、本書のような女性の作家も少なくない。だが、本書のような味わいをもった作品はめずらしい。
その点がおそらく評価されて、2018年度の「ニューアカデミー文学賞」にノミネートされたのだ。2018年度はノーベル文学賞が諸般の事情で授賞されないことになり、代わりに設けられた文学賞が「ニューアカデミー文学賞」だ。それの候補作になったというのは本当だろうかと多くの読者は思うのではないか。それくらい地味でぱっとしない印象がある。
*
しかし、途中からじわじわと、題名の「小川」のように、ちょろちょろとした流れが読者の中に沁み通ってくる。原題の ru はフランス語読みすれば「リュ」で「小川」「小さな流れ」を意味する古いことばだ。ベトナム語では「子守歌」「揺籃」を意味するという。
著者の Kim Thuy キム・チュイは1968年、ベトナムのサイゴン(1976年以降の名称はホー・チ・ミン市)に生まれた。
キム・チュイは10歳の時(1978年頃)、ベトナムを離れてボート・ピープルとなった。国連難民高等弁務官事務所が運営するマレーシアの難民キャンプに到着した後、カナダのケベックに渡り、最終的にはモントリオールに落ち着いた。
当時のベトナムは、ベトナム戦争(1955-75)後のベトナム人民軍(ベトナム共産党の党軍)の政権下にあった。ベトナム戦争の終結を画するのは1975年4月30日にベトナム人民軍がサイゴンを支配下においたことだが、この出来事をベトナムからの移住民のコミュニティや米国(ベトナム戦争で共産主義と戦った)は「サイゴンの陥落」と呼び、ベトナム社会主義共和国は「サイゴンの解放」と呼ぶ。
*
本書を読むと、当時のベトナムが本当に「解放」された状態にあったのか、深刻な疑問が湧いてくる。やむにやまれず母国を離れざるを得なかった多くの人々の無念は、本書で断片的にスケッチされるが、多くのことばを費して語られないだけに、かえって背後にある事情を読者は段々と思い描くようになってゆく。
*
作者が両親から受取ったものが、作者の旅を支えたことが短い言葉から伝わる。
両親は私と兄たちに残してやれるお金はないと言っていたけれど、すでにたくさんの思い出を残してくれた。自然の美しさや言葉の大切さ、感動すること、そして、永遠に夢まで歩くための足をくれた。旅を続けるための鞄には、それだけで十分だろう。そうでなければ荷物を持たなくてはならず、いたずらに旅路を困難にしてしまう。
ベトナムにこんな諺がある。「髪の長い人だけが、恐れを抱く。髪がなければ、髪を引く人はいないから」それで、自分の身の丈以上の物を手にしないようにしている。
この「荷物」とは何だろう。モノとしての荷物の意味だろうか。いや、「旅を続けるための鞄」に入れるものは「自然の美しさや言葉の大切さ、感動すること、そして、永遠に夢まで歩くための足」というのだから、ふつうの荷物ではないだろう。
この「荷物」こそ、ベトナムからのディアスポラが背負ってしまいかねない何かなのだ。そんな「荷物」があれば旅路は困難になる。
けれども、その「荷物」を棄てること、言い換えれば「自然の美しさや言葉の大切さ、感動すること、そして、永遠に夢まで歩くための足」以外のものを棄てることが、いかに困難なことか。それが本書を読んでいると、だんだん分かってくる。読者の心の底まで小さい流れが沁み通って、その名づけ得ない「荷物」の堆積がだんだんと溜まってゆくのだ。
その澱のような負荷と、澄みきった美しいものとの両極に引き裂かれるような感覚を覚えながら、読者は本書を読み進む。それが本書に独特の感触を与えている。
本書はフィクションに分類されているらしいが、各章の長さがまちまちであること、各章のつながりがロジカルというよりメトニミカルであることから、散文詩の味わいがある。
*
「歯と髪はその人の源だ」とは、著者の母がよく言っていたこと。著者たちの〈歯がきちんと整えられていることを母は望んだ〉という。なるべく身軽に旅を続けるにしても、歯と髪とはその人についてまわるのである。
日本の文学意識の根源を異人のもたらした文学にみる
折口信夫『日本文学の発生』

折口信夫の文学論のうち、日本文学の発生にかかわる根本問題を、次の3種の文献を引きつつ考察したもの。
・播磨風土記
・神武紀
・神代紀
もちろん、すべて漢文で引用されている。
まず、前提として、日本の国土に対して、他界が想定された。他界の生活様式は、日本の事情と、すべて正反対の形であると考えた。
日本文学の起源がつくられたとき、その起源をつくった時代の人々は、それがことごとく空想の彼岸の所産であると考えた。その彼岸と此岸との両方の国土の消息に通じた者が考えられ、その者がもたらす詞章が、のちに文学となるべき初めのことばであった。
周期的にこの国を訪問する者を異人、または、まれびと、と呼んだ。
その異人がもたらす詞章は威力をもつと信じられた。その威力は、その詞章に含まれている発言者の霊力の信仰が変化したものであった。
この詞章の威力が、そうした威力を持つものと信じられたがゆえに、長く保持され、次第に分化して、結局、文学意識を生じるに至ったと、折口信夫はいう。
*
この折口がいう詞章の威力は、万葉集における、柿本人麿や山上憶良が詠った言霊(ことたま)と似通っているように思える。ところが、驚くべきことに、日本に特有の言葉の霊力と思われる言霊の、そもそもの起源と考えられる原初の詞章の威力が、異人に由来するというのだ。
もし、そうだとすると、われわれは言霊に関する思想を、根本から見直す必要に駆られる。
いろいろな意味で、日本文学を根底から考えさせる論考だ。
英詩としても見事なリービ英雄氏の英訳万葉集
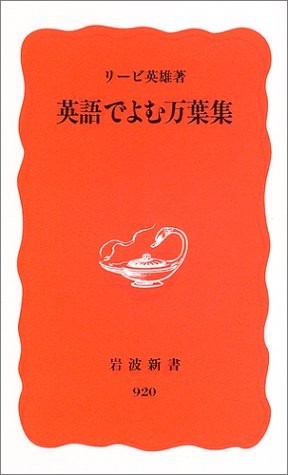
リービ氏の万葉集関連の著書では最も親しみやすい書。
〈約50首の対訳それぞれに作家独自のエッセイを付す,「世界文学としての万葉集」〉を語った本。
リービ氏の言わんとするところを最もよく伝えるのは、おそらく、この書でなく、Ian Hideo Levy, Hitomaro and the Birth of Japanese Lyricism (Princeton UP, 1984) か、あるいは、リービ英雄『Man’yo Luster―万葉集』(ピエブックス、2002) の方だろう。なぜなら、それらの書では英文で書いているから。残念ながら、本書の日本語は達意の表現とはいかず、真意を汲みとるのに苦労することがある。
それでも、本書は、意外な歌または意外な長歌の一部を選んでいることと、英詩として興味深い翻訳があることと、日本人にはない創見により、読みごたえがある。
人麿学者としてのリービ氏が柿本人麿を扱った部分に読むべきところが多いのは当然としても、もう一人の大歌人、山上憶良について述べているところが、人麿と好対照をなし、本書の幅を広げている。願わくは、この対比の部分をもっと掘りさげてほしかったが、新書の限られた枠では総花的になるのはやむを得なかったか。
ひとつ本書の意外な効用としては、万葉集を原文で読むよりも、英訳で読む方が現代の日本人には分りやすいということがある。万葉集には今も解釈不能の難読箇所が残っているが、そういう箇所も含め、現代人には通じにくい1300年前の日本語が、現代英語により、生き生きとひびくことが本書では何度も起きる。それは心躍る読書体験だ。
*
心が動かされる瞬間は多いけれども、一つだけ例を挙げておこう。柿本人麿が妻と別れる場面の歌だ (巻2.136)。
青駒の足掻を早み 雲居にそ 妹があたりを 過ぎて来にける
(青駒の歩みが早いので、雲居の彼方のはるか遠くまで、妻の住むあたりを過ぎて来てしまった。)
これをリービ氏は次のように英訳する。
The quick gallop
of my dapple-blue steed
races me to the clouds,
passing far away
from where my wife dwells.
「青駒の足掻を早み 雲居にそ」を氏は 'The quick gallop / of my dapple-blue steed / races me to the clouds' と訳す。gallop / dapple の /æ/ の母音韻に耳を奪われる間もなく、'races me to the clouds' と、おっと言わせる表現で締める。この race の他動詞としての用い方(「全速力で走らせる」)は意表をつくが、これしかないと思わせる説得力がある。猛スピードで馬に運ばれた先は 'clouds' である。読み手の想像力の中をあっという間に駈けぬけ、天へと駆けのぼる。見事であると同時に痛切だ。
もう、これほど妻から離れてしまったのである (passing far away / from where my wife dwells)。そのことを知った詠い手は、far away の行末で、本来、文法的には次行に続く句跨り (enjambment) の箇所なのだが、かすかに余韻を置き、小さな嘆息をしているように聞こえてくる。「ああ、はるか遠くだなあ、妻の家は」と。
このように、リービ英雄氏の英訳は、英詩として、じゅうぶん鑑賞に堪え、それだけでなく、そこから元の万葉集の原文を振りかえらせ、さらに深く味わわせてくれる。






