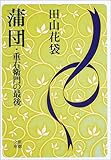田山花袋『蒲団』
田山花袋の『蒲団』(1907)が日本の自然主義小説の方向を定めたといわれること、日露戦争の戦後文学の代表作であること、いづれも周知のことである。
この小説の基本的枠組について少しく考える。定式化するならば、この種のパワーポリティクスは<A が自らの B への影響力を C と競う>となる。
政治方面で例を挙げると、ウクライナのポロシェンコ大統領が EU 加盟の前提となる経済協定に署名した。2014年6月27日のことである。ウクライナを自らの影響下にとどめておきたいロシアのプーチン大統領は反発した。この関係を上の図式にあてはめれば
A = ロシア、B = ウクライナ、C = EU
となる。一方、本書をこの図式にあてはめると
A = 時雄、B = 芳子、C = 田中
となる。妻子ある作家の竹中時雄のところへ横山芳子という女学生が弟子入りする。その師弟関係の中でひそかに時雄は芳子に思いを寄せる。そのうちに、芳子の恋人である田中秀夫が登場し、芳子を追って東京へ来る。
小説の主題として珍しくない。問題はその文体にある。この文体が当時の文壇に爆発のごとき衝撃を与えたのはなぜか。
理論的に二つ考えられる。ひとつに、著者は自分の「写実的傾向」(realistic tendency)が師である松浦辰男の歌論に発すると述べている。その論は、「実感を重んじ、技巧を去って我に忠実でなければならぬという歌論」(吉田精一)であった。皮肉というか必然というべきか、この「我に忠実」の部分が私小説となって結実することになる。もうひとつは、「かくされたものをあらはす」(『露骨なる描写』)技法である。人間の獣性をあばくモーパッサンの影響があるかもしれない。
現代の読者はこれをどう読むだろうか。ひょっとすると、ライトノベルの元祖のように読むかもしれない。ものすごく読みやすい。前へもどって考えさせるところがない。理解不能な展開が現れることもなく、すらすらと進んでゆく。現代に発表されたとしたら、驚きを与える要素はほとんど皆無である。
ただし、時雄が恋を考えるときの語彙「神聖の霊の恋」「霊肉共に許した恋人」などは、現代の読者にはあまりぴんとこないかもしれない。自然主義文学者たちのうちに、青年期をキリスト教の影響のもとにすごした者が多いことはよく知られている。上記の三人の主要登場人物のうち、田中は同志社で神学を修め、芳子はミッション系の神戸女学院に学んだ。
評者が本書に関連して関心を抱いていることは、柳田国男と自然主義との関係である。柳田においての自然主義は日本のそれでなく、西欧のそれであるといわれる。ところが、柳田と花袋とは交友関係にあった。花袋は日本的自然主義の典型と目される。彼らの間ではそのあたりをどう捉えていたのであろうか。