中央大学人文科学研究所 編『ケルト 口承文化の水脈』(中央大学人文科学研究所研究叢書、2006)
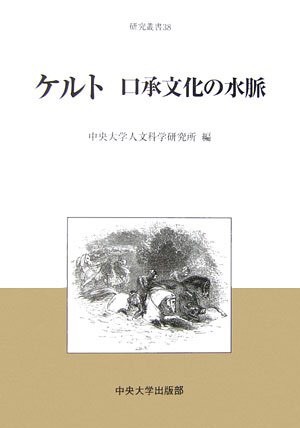
2001年度に発足した《ケルト口承文化研究》共同研究チームの成果の4冊目(2006)。
ケルト口承文化の水脈は「太古の無文字社会に遡り、ケルト的な口承性を孕みながら書承の世界を生み出して現代まで綿々として流れている」。
口承というからには声の文化なのだが、声は発せられた瞬間に消える。
ところが、この口承文化が「共同体の記憶を貯蔵」することになるのは、そこに声による記憶のメカニズムが働くからだ。形態は多様で、「物語や民間説話、聖人伝、詩、歌、バラッド、祈り」などさまざまな「声の通路」が話し手と聞き手の間に開かれる。
本書は長い間愛読してきたが、その中身が一般にはほとんど知られていないので、収められた論文名を次に掲げる。
- 松村賢一「巨人、この異様なるもの──ゲーリック口承文化の源流をたどる──」
- 盛 節子「コロンバ伝承の展開と歴史的背景」
- 木村正俊「『キルフッフとオルウェン』における語りの構造と様式」
- 渡邉浩司「『ブルターニュの短詩』に見られる『口承性』をめぐる考察」
- 松井優子「初期スコットランド小説と複数の声」
- 北文美子「語りなおされたフォークロア──『奔放なアイルランド娘』と楽園幻想──」
- 真鍋晶子「語る音楽、うたう音楽──『死者たち』再読──」
- 栩木伸明「『多声』によるアイルランド文学の創成──ジョン・モンタギューの長編連作詩『荒蕪地』をめぐって──」
- キアラン・マーレイ「ディンシャナハスとアイデンティティ──カーローの場合──」
- 三好みゆき「語られる『ケルト』──『ケルト懐疑』の語りをめぐって──」
- 鈴木哲也「ノンコンフォーミズムの語り」
- 小泉 凡「ラフカディオ・ハーンにおける口承文化の受容と継承」
- 小菅奎申「口承から口誦へ」
以上の通り、驚くほど多様なトピックが扱われている。一例として第5章をみると、そこでは「スコットランドにおけるさまざまな声」を拾う。つまり、ケルトといえば指す地域はアイルランド、スコットランド、ウェールズ、ブルターニュなどいろいろあるが、そのそれぞれの地域にも多くの声があるということだ。
スコットランドにおける声としてスコットランド英語(Scots)、スコットランド・ゲール語、および標準英語の少なくとも三つがある。たとえば、この最初の例、スコッツ語を用いた小説の例として、エリザベス・ハミルトンの『グレンバーニーの村人たち──農夫の炉辺向けのお話』The Cottagers of Glenburnie(1808)が挙げられている。どれくらい普通の英語と違うかというと、たとえば村人の発言「そんな面倒、まっぴらごめんだね」は 'We cou'dna be fashed' となる。この fash というのは悩ます(trouble)の意の動詞だが、スコットランド以外ではめったに耳にしないだろう。ただし、同根の語 fastidious (めんどうな)は普通の英語の語彙に入っている。
一種の多声文化であるケルト口承文化の豊穣さがよく分かる書だ。